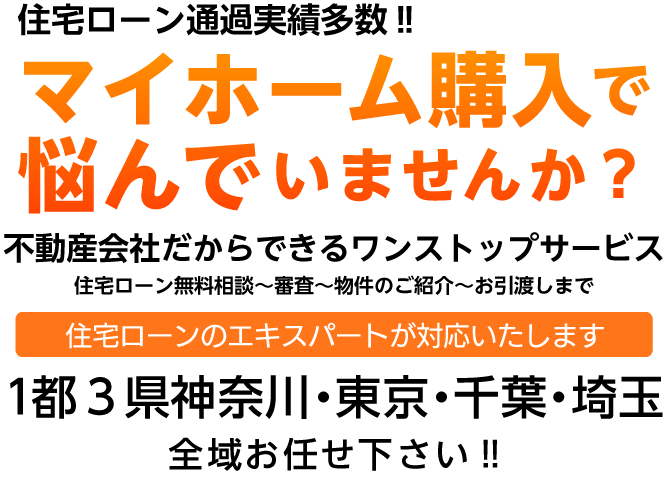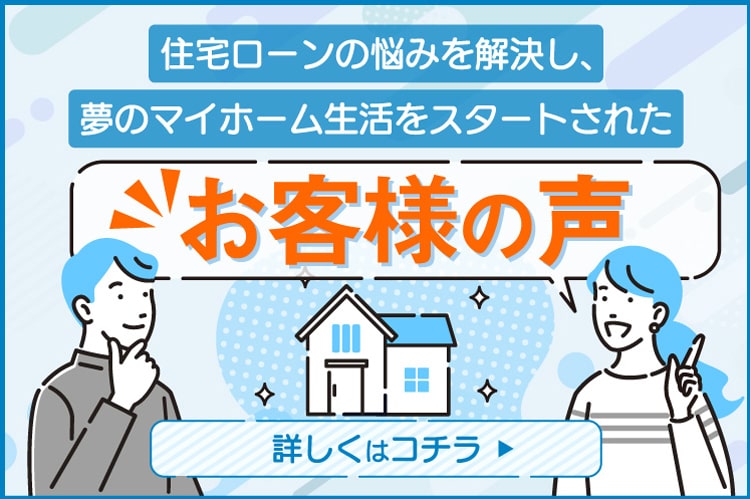マイホームの夢をかなえる住宅ローンとして人気の「フラット35」ですが、近年この制度を悪用する不正利用が相次ぎ、問題となっています。
本来は自分が住む家を購入するためのローンにもかかわらず、投資目的や転売を前提とした契約など、制度の趣旨に反する使い方が増加傾向にあるのが現状です。
悪質な業者の勧誘や書類の操作によって、気づかぬうちに不正に関与してしまうリスクもあるため、正しい理解が不可欠です。
この記事では、フラット35の概要から不正利用の手口、実際のトラブル事例、対策までをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
- フラット35の不正利用(不適正利用)とは?
- フラット35を不正利用させる詐欺の手口
- フラット35を不正利用させる悪徳不動産会社の誘い文句
- フラット35を不正利用に関わったときの法的リスク
- フラット35の不正利用によるトラブルを避けるポイント
- 不正利用を避けて安心のローンを組むなら住宅ファクトリー
疑問があればぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
フラット35の不正利用(不適正利用)とは?
「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している住宅ローンです。長期固定金利で資金計画が立てやすく、自己居住用の家を購入する人に広く利用されています。
一方、投資用や転売目的といった本来の趣旨に反する利用が後を絶たず、不正利用として問題視されています。
なかには、不動産会社の勧誘で制度のルールを誤解したまま契約してしまうケースもあり、注意が必要です。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
フラット35の不正利用による被害件数
住宅金融支援機構の調査によると、2018年10月から2019年8月にかけて、不正利用が疑われる113件の融資申込について調査が実施されました。そのうち、105件で不正利用が確認されています。
確認された不正の多くは、「自己居住用」と偽って投資目的で住宅を購入し、フラット35を利用していたというものでした。物件価格の水増しや、書類の偽装もあわせて行われていたケースが多く、組織的な関与があったとされています。
以下は、調査対象となった住宅購入者と物件の特徴です。
| 特徴 | 件数 | 割合 |
| 20代から30代前半の単身者 | 95件/113件 | 84% |
| 年収は300〜400万円台の会社員 | 73件/113件 | 65% |
| 全件中古住宅で、価格は1,000万〜2,000万円台 | 90件/113件 | 80% |
| 東京近郊の通勤圏内にあるファミリータイプのマンション | 93件/113件 | 82% |
| フラット35以外にも多額のリフォームローンや借入があるケース | 101件/113件 | 89% |
※参考:フラット35の不適正利用懸念事案に係る調査結果の公表|住宅金融支援機構
調査では、20〜30代前半の単身者によるフラット35の不正利用が多く確認されました。対象となった物件の多くは、中古のファミリータイプマンションで、購入後は自己居住せずに賃貸に出されていたケースも見られます。
事例の中には、「フラット35でもサブリースで収益が出る」「居住用と申請すれば問題ない」といった説明を受け、知らないうちに不正利用に加担していたと見られるものもあります。
制度を正しく理解せずに利用したり、安易な言葉に流されてしまうことが、思わぬトラブルや法的リスクにつながるケースもあるため、注意が必要です。
※参考:【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないために:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
フラット35を不正利用させる詐欺の手口
フラット35は本来、自己の居住を目的とする住宅購入者を対象としたローンですが、その仕組みを悪用する手口が複数報告されています。
ここでは、実際に問題となった主な手口について具体例を交えて紹介します。
- 住民票を移動させて自己居住を偽装
- 収入の水増し
- 物件価格の水増し
- 頭金の偽装
- 虚偽の入居予定申告
住民票を移動させて自己居住を偽装
非常に多い手口のひとつが、住民票だけを移して実際には住まずに貸し出す、いわゆる「居住実態の偽装」です。
フラット35は自己居住用であることが条件ですが、投資目的で購入した物件に住んでいるように見せかけるために、形式上だけ住民票を移すケースがあります。
申請時には「住む予定」としていても、初めから貸し出すつもりで物件を取得する行為は明確な不正利用にあたります。
実際に、投資目的で購入した物件に住まず、後に住宅金融支援機構から居住確認を受け、ローンの一括返済を求められた事例が報道されました。
※参考:若者が陥る不動産投資のワナ 「フラット35」の不正利用が相次ぐ【WBS】|テレ東BIZ
収入の水増し
本来の収入では希望額の融資を受けられない場合に、年収を実際より多く見せて審査を通そうとする不正も発生しています。中には、源泉徴収票や確定申告書の数値を改ざんするようなケースまで報告されています。
数字だけで通ってしまえば、一時的には成功に見えるかもしれません。しかし、将来的に返済が滞ったり、不正が発覚したりした場合は、重い責任を問われることもあるでしょう。
収入に見合わない借入は、家計にも精神的にも大きな負担になりかねません。テレ東の取材では、年収が約100万円水増しされた書類で融資を通されたケースも明らかになっています。
※参考:若者が陥る不動産投資のワナ 「フラット35」の不正利用が相次ぐ【WBS】|テレ東BIZ
物件価格の水増し
売買契約書上の価格を実際よりも高く記載し、その金額でフラット35を申請する手口もあります。
表向きは高額な物件として契約が進められますが、実際には水増しされた分が別の形で戻されたり、業者側の利益として処理されたりするケースが報告されています。
こうした方法で引き出された余剰な資金は、当然ながらローン返済の対象にもなり、不正の代償を借主が背負うことになりかねません。
報道では、実際に不動産会社の元幹部が「融資を通すために売買価格や自己資金額を改ざんした」と証言しており、同様の不正が多数の契約で行われていたことが明らかになっています。
※参考:マンション不正融資、「アルヒ関与」深まる疑念 年収200万円台の低所得者層もターゲットに|建設・資材|東洋経済オンライン
頭金の偽装
本来、頭金を入れていないのに、書類上は支払ったことにして申請するケースもあります。よくあるのは、販売価格を水増しして頭金を捻出したように見せかけるケースです。
こうした偽装は契約上の信頼を損なうだけでなく、最終的には借主が負担を背負い込むリスクにもつながります。
このような水増しに関しても、不動産業者の元幹部が「FC社員の指示で、融資が下りるよう賃料や自己資金額を改ざんしていた」と証言しており、数十件に及ぶ不正が確認されていると報道されました。
※参考:マンション不正融資、「アルヒ関与」深まる疑念 年収200万円台の低所得者層もターゲットに|建設・資材|東洋経済オンライン
虚偽の入居予定申告
フラット35は本来、借主自身が居住することを前提とした住宅ローンです。
しかし、実際には住む予定がないにもかかわらず、住民票だけを移して自分が住む家として見せかけるケースが問題になっています。
初めから賃貸目的でありながら、体裁だけ整える手口も多く、郵便物の転送や簡単な家具の設置などで入居実績があるように見せかける例も見られます。
実際に、こうした手口によって不正利用が発覚し、住宅金融支援機構からローンの全額返済を求められた事例も報道されており、20〜30代の若年層が多く巻き込まれています。
※参考:若者が陥る不動産投資のワナ 「フラット35」の不正利用が相次ぐ【WBS】|テレ東BIZ
フラット35を不正利用させる悪徳不動産会社の誘い文句
フラット35の不正利用は、利用者が意図せず巻き込まれてしまうケースも少なくありません。
特に注意が必要なのが、制度をよく知らない若年層に対し、悪質な不動産会社が巧みに勧誘してくるパターンです。ここでは、実際によく使われる「誘い文句」の具体例を紹介します。
- 「契約書を2つ作成しておきましょう」
- 「金融機関には「自己居住用」と説明すれば問題ありません」
- 「手続きは弊社がやるので金融機関とは話さないでください」
- 「収入が少なくても弊社がなんとかしますよ」
- 「返済中のローンをフラット35で一本化しましょう」
「契約書を2つ作成しておきましょう」
表向きの内容と実際の取引内容が異なる2種類の契約書を用意し、「こちらを金融機関に出せば問題ありません」といった説明をされることがあります。
しかし、事実と異なる内容で契約書を作成・提出することは、後々大きなトラブルや責任問題につながる可能性があります。
一般的な不動産取引では、実際の売買内容に基づいて契約書を1通のみ作成するのが通常の手続きです。複数の契約書を使い分けるような方法には注意が必要です。
「金融機関には「自己居住用」と説明すれば問題ありません」
本来は住む予定がないにもかかわらず、「住む予定ですと言えばローンは通りますよ」といった説明も要注意です。
仮に一時的に通ったとしても、のちに居住実態が確認されなければ、違反として指摘される可能性があります。通常であれば、会社はルールに沿った正しい案内をしてくれるでしょう。
「手続きは弊社がやるので金融機関とは話さないでください」
「当社が全部対応するので、お客様は何も話さなくて大丈夫です」と言われると安心しそうになりますが、実際には収入情報や勤務先の内容が改ざんされるおそれもあります。
通常の不動産会社であれば、必要な書類や申請の流れを丁寧に説明したうえで、本人確認を含めた対応を進めるのが一般的です。説明を省くようなやり取りには注意が必要です。
「収入が少なくても弊社がなんとかしますよ」
年収がローン審査の基準に届かない場合でも、「こちらで調整するので問題ありません」と言ってくる業者には注意が必要です。
中には、年収を水増しした源泉徴収票や確定申告書を作成し、虚偽の情報で審査を通そうとするケースもあります。
こうした行為は重大な不正にあたり、発覚すれば借主側にも重い責任が及びます。通常の不動産会社であれば、収入と返済のバランスを見ながら、無理のない資金計画を提案するのが一般的です。
「返済中のローンをフラット35で一本化しましょう」
フラット35は、あくまで「自分が住む住宅を新たに購入する場合」に利用できるローンです。
他の借入金をまとめる目的で使うことはできません。
それにもかかわらず、「住宅購入に見せかけてローンを組み替えましょう」と提案してくる業者がいます。こうした使い方は制度の趣旨に反しており、契約の取消しや違約金請求といった深刻なトラブルに発展するリスクがあります。
制度を正しく理解している不動産会社であれば、このような案内をすることはありません。
フラット35を不正利用に関わったときの法的リスク
フラット35の不正利用は、単なるルール違反では済まされない場合があります。
実際に被害や損害が生じていれば、借主自身にも法的な責任が問われる可能性があり、状況によっては以下の両面で責任を負うことになります。
- 民事上の責任(損害賠償責任など)
- 詐欺罪
民事上の責任(損害賠償責任など)
フラット35に関する不正行為によって、金融機関や関係機関に損害が生じた場合には、民事上の責任を問われる可能性があります。
「自己居住」と偽って申請したケースに限らず、申請書類に虚偽の記載をしたり、提出資料を改ざんしたりする行為も対象です。
また、不正に資金を取得したと判断されれば、不法行為(民法第709条)や債務不履行(民法
第415条)として、損害賠償責任が発生することがあります。
| 【民法 第709条】(不法行為による損害賠償):
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
※引用:民法|e-Gov 法令検索
この条文は、他人に損害を与えた場合に、その責任を取る必要があるというものです。たとえば、収入を水増しして融資を引き出し、金融機関が損害を受けた場合などが該当します。
| 【民法 第415条】(債務不履行による損害賠償):
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
※引用:民法|e-Gov 法令検索
上記は、契約上の約束を守らなかった場合に生じた損害を補償しなければならないという内容です。フラット35の契約では「自分が住むこと」が前提で、実際には住まなかった場合、この条文が適用される可能性があります。
詐欺罪
不正利用の内容や程度によっては、民事責任にとどまらず、刑事事件として扱われるケースもあります。
特に、虚偽の申告や書類の改ざんによってローン審査を通し、資金をだまし取ったとみなされれば、「詐欺罪」に問われるおそれがあります。
【第二百四十六条】(詐欺):
|
※引用:刑法|e-Gov 法令検索
これは、他人をだましてお金を受け取った場合などに適用される刑事罰で、不正に融資を引き出した場合はこれにあたると判断されることがあります。
たとえば「住むつもりがある」としてフラット35を申請し、実際には最初から賃貸目的だった場合など、明確な意図をもって金融機関を欺いていたとされれば、厳しい処分を受ける可能性も否定できません。
フラット35の不正利用によるトラブルを避けるポイント
フラット35は、マイホームの取得を支援する住宅ローン制度として、多くの方に利用されています。
一方、制度の内容をよく理解しないまま申請を進めてしまうと、「不正利用」と見なされ、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。
ここでは、不安なく手続きを進めるために、申し込み前に確認しておきたいポイントを整理しました。
- 利用条件・利用目的を正しく理解する
- 申込書の内容を漏らさずに確認する
- 物件が居住可能かどうかを確認する
- 不動産会社(施工会社)の実績や評判を確認する
- 無理のない返済計画を立てる
- 疑わしい勧誘があった場合は専門家に相談する
利用条件・利用目的を正しく理解する
フラット35を利用するには、申込者や物件、借入れ条件に関していくつかの要件があります。
特に、資金の使い道や年収に対する返済負担率など、基本的な条件は事前に確認しておくことが大切です。
| 項目 | 内容 |
| 年齢要件 | 借入時に満70歳未満(親子リレー返済の場合は70歳以上も可) |
| 国籍 | 日本国籍/永住者/特別永住者 |
| 資金使途 | 自己または親族が居住する住宅の建築・購入(新築または中古) |
| 対象外 | 投資用・賃貸用住宅/事務所や店舗のみの建物など |
| 総返済負担率(※) | 年収400万円未満:30%以下 年収400万円以上:35%以下 |
| 借入対象物件 | 技術基準を満たした住宅(床面積・耐久性など一定基準あり) |
※年間の返済額の合計が、その人の年収に対してどの程度の割合を占めるかを示す指標
※参考:【フラット35】ご利用条件:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
こうした条件を十分に理解せずに手続きを進めると、後になって契約違反と判断されることもあります。制度の仕組みを正しく把握し、自分のケースに当てはまるかどうかをしっかりチェックしておきましょう。
申込書の内容を漏らさずに確認する
フラット35を申し込む際には、年収や勤務先、居住予定など多くの情報を申請書に記入します。内容に不備があると審査に影響するだけでなく、万が一虚偽があれば不正利用と見なされる可能性もあります。
書類は必ず1つずつ目を通し、自分が記載した内容と相違がないかをしっかり確認することが大切です。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
物件が居住可能かどうかを確認する
フラット35は「実際に居住する住宅」を対象としたローンです。そのため、購入予定の物件が居住用として適切かどうか、しっかりと確認しておくことが大切です。
用途が店舗や事務所になっていないか、構造や面積が住宅金融支援機構の基準を満たしているかなど、不動産会社任せにせず、ご自身でも条件をチェックするようにしましょう。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
不動産会社(施工会社)の実績や評判を確認する
物件選びだけでなく、扱う不動産会社や施工会社の信頼性も大切です。
これまでの販売実績や施工例、利用者からの評判などを事前に調べておくことで、安心して手続きを進めやすくなります。
問い合わせへの対応が曖昧、説明を省こうとするなどの場合は注意が必要です。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
無理のない返済計画を立てる
住宅ローンは長期にわたる契約になるため、毎月の返済が家計に無理なくおさまるかどうかを事前にしっかり検討することが大切です。
「借りられる金額=返せる金額」ではないことを前提に、生活費や教育費、将来の出費も見越した上で返済プランを立てましょう。
不安がある場合は、金融機関やファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
疑わしい勧誘があった場合は専門家に相談する
「手続きは全部こちらでやるので」「住む予定と伝えれば大丈夫です」など、少しでも違和感を覚える勧誘があったら、早めに専門家に相談しましょう。
住宅ローンに詳しい弁護士や消費生活センター、不動産の専門窓口などが力になってくれます。一人で判断せず、第三者の意見を聞くことがトラブル防止につながります。
※参考:住宅ローン:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】
フラット35の不正利用に関するよくある質問
ここでは、不正利用に関連してよく寄せられる質問について、実際の事例や制度の仕組みをもとにわかりやすく解説します。
- 不正利用の事実はどのようにしてばれる?
- 意図せずに住宅ローンを不正利用してしまったらどうする?
- 不正利用に関する実際の裁判結果はある?
不正利用の事実はどのようにしてばれる?
フラット35を不正に利用していた場合でも、融資後の確認や調査によって発覚するケースは少なくありません。
特に多いのが、「居住実態がない」と見なされるケースです。たとえば、住宅金融支援機構から送られてくる「居住確認の書類」に応答がなかったり、現地調査で生活の形跡が見られなかったりすると、虚偽の申告が疑われます。
また、申込時に提出した収入証明や勤務先の情報と、実際の内容に食い違いがあった場合にも調査が入ることがあります。
調査の結果、不正が確認されると、融資の一括返済を求められたり、契約の取り消しや法的措置に発展したりするおそれもあるため注意が必要です。
意図せずに住宅ローンを不正利用してしまったらどうする?
不動産会社の説明を信じて書類を提出したものの、後になって違反と気づくケースも少なくありません。このような場合には、できるだけ早く金融機関や住宅金融支援機構に相談し、現状を正直に説明することが大切です。
指摘される前に自ら申し出て対応することで、事態が悪化するのを防げる可能性もあります。特に、虚偽の申告や偽装に関与していない場合には、状況を正確に伝えることで悪質な意図がなかったことを示す材料にもなります。
信頼できる専門家に相談しながら、適切な対応を進めましょう。
不正利用に関する実際の裁判結果はある?
不正利用に関する実際の判例も報告されています。たとえば、2024年2月にSBIアルヒのフランチャイズ店の元社員と関係者が、不正融資に関わったとして詐欺容疑で逮捕されています。買主側も虚偽申請に関与し、刑事責任を問われた事例です。
その後の民事訴訟では、投資用マンションローンに関して買主が訴えたケースで、2025年3月26日付の東京地裁判決により原告の請求は棄却され、アルヒ側の主張が認められました。
※参考:フラット35の融資金不正詐取事案を巡る報道について|SBIアルヒ株式会社
※参考:マンション不正融資、「アルヒ関与」深まる疑念 年収200万円台の低所得者層もターゲットに|建設・資材|東洋経済オンライン
不正利用を避けて安心のローンを組むなら住宅ファクトリー
フラット35は、自分や家族が安心して住む家のために設けられた住宅ローン制度です。
しかし、近年では不正利用をめぐるトラブルが増えており、制度を正しく理解することがますます重要になっています。
住宅ファクトリーは、住宅ローンに特化した家づくりを通じて、お客様が安心して住まいを手に入れられるようサポートしています。フラット35などの制度を正しく活用し、不正利用につながるような営業や提案は一切行っておりません。
また、マイホーム購入時の負担を軽減する「住宅ローンの一本化」など、資金計画を支える仕組みもご用意しています。
制度のリスクを避け、納得のいく住まい選びをしたい方は、ぜひご相談ください。
疑問があればぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!