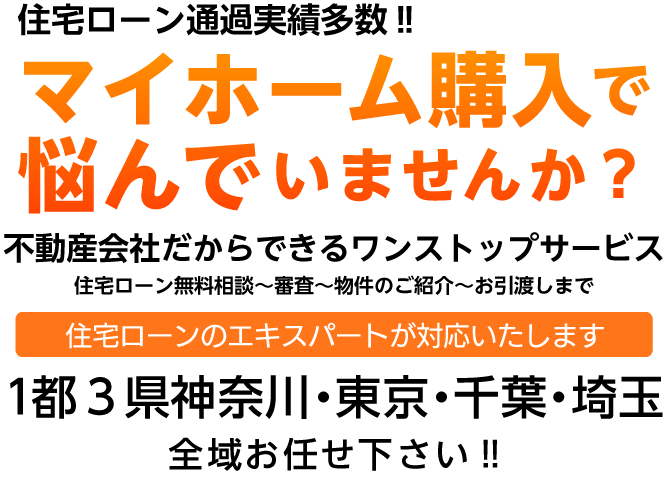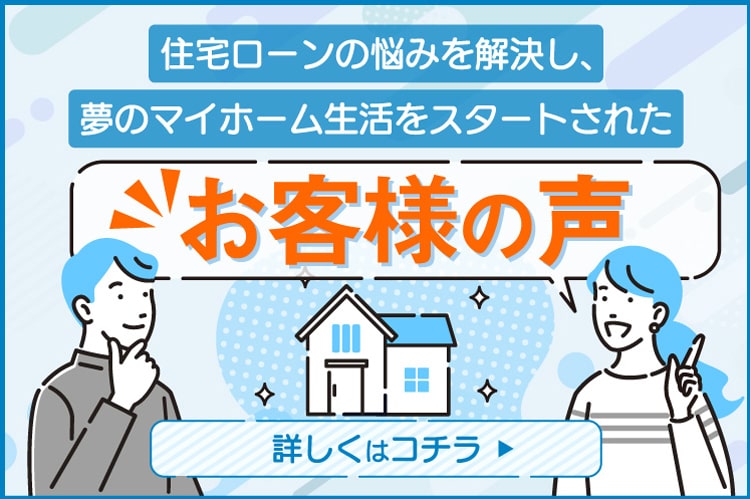この記事では、老後の住まいは持ち家と賃貸どちらがお得かについて解説します。
持ち家と賃貸には、それぞれに明確なメリットとデメリットが存在します。
老後という”人生の後半戦”において、どちらの選択がより安心、かつ現実的であるのかを見極めることは、ライフプラン全体に大きく影響を与える重要なテーマです。
この記事では、持ち家と賃貸それぞれのケースについて、長期的な視点からシミュレーションを行い、老後の住居費用を比較・分析します。ぜひ、参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 【比較】老後の住まいは持ち家と賃貸どちらがお得?
- 比較でわかった!老後に持ち家で暮らすメリット・デメリット
- 比較でわかった!老後に賃貸で暮らすメリット・デメリット
- 老後の持ち家で後悔しないためのポイント
疑問があればぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
【比較】老後の住まいは持ち家と賃貸どちらがお得?
一概にはいえませんが、持ち家の方が賃貸と比べて資金面・費用面などではお得なケースが多いといえます。
理由は複数ありますが、特に大きいのは高齢者が新たに賃貸住宅を借りるハードルの高さや、住み慣れた環境で生活を維持できるといった持ち家のメリットが大きい点などです。
年齢を重ねるにつれ、収入や健康状態、保証人の有無などが賃貸契約の審査で不利に働くケースが少なくありません。
また、賃貸では家賃が一生発生し続けるのに対し、持ち家はローンさえ完済していれば、税金や修繕費などを除けば大幅にコストを抑えることが可能です。
ここからは、持ち家と賃貸の違いとして以下を比較します。
- 初期費用の比較
- 資産価値の比較
- 住宅ローン返済・家賃負担の比較
- 維持費用(ランニングコスト)の比較
- 住み替え・引越し難易度の比較
- リフォーム・リノベーションの自由度の比較
- 暮らしやすさ・安心感の比較
初期費用の比較
住宅を購入する際は、頭金・登記費用・仲介手数料など購入時に多額の資金が必要です。
新築・中古問わず、初期費用は数百万円単位にのぼるケースもあります。一方、賃貸の場合は敷金・礼金など数十万円程度に収まりやすく、初期投資は比較的抑えられるでしょう。
持ち家・賃貸それぞれに必要な初期費用の目安は以下のとおりです。
| 家の種類 | 初期費用 |
| 賃貸 | 50~200万円 |
| 持ち家 | 0~200万円 |
一見すると賃貸の方がお得に見えますが、高齢者が新たに賃貸を借りるには保証人の確保や審査条件が厳しくなることがあり、必ずしも簡単とはいえません。
また、賃貸は毎月家賃の支払いなどが発生するため、住宅ローンを完済しているのであれば持ち家の方がトータルコストが安くなるといえます。
資産価値の比較
持ち家には資産価値があり、将来的に売却や賃貸運用も可能です。
立地や物件の状態によっては資産価値をある程度維持でき、老後の生活資金に充当することもできるでしょう。
一方、賃貸住宅に支払う家賃は蓄積されず、長期間住んでも資産として残ることはありません。資産形成という観点では、持ち家の方が優位といえます。
住宅ローン返済・家賃負担の比較
老後に住宅ローンを完済している場合、持ち家における住居費は税金やメンテナンス費用などで済みます。
一方、賃貸は年齢に関係なく家賃が継続し、退職後の収入で賄うには負担が大きくなる場合があります。また、家賃の上昇リスクや更新料の発生も考慮が必要です。
結果的に、長期的な支出総額では持ち家の方が安定しやすい傾向があります。
維持費用(ランニングコスト)の比較
住宅を所有する場合は、固定資産税・修繕積立費・火災保険などの維持費が継続的に発生します。年数が経つごとに修繕の頻度が増え、大きな出費に影響することも考えられます。
賃貸物件ではこれらの費用の多くを大家側が負担するため、入居者の管理コストは抑えられますが、賃料にそれらが織り込まれていると考えるべきです。
住み替え・引越し難易度の比較
賃貸住宅はライフスタイルの変化や身体状況に応じて柔軟に移動できますが、高齢者にとっては新規契約のハードルが上がるのが現実です。
審査や保証人の条件が厳しく、希望する物件に入居できない場合もあります。
持ち家は転居の自由度が低く、売却や賃貸経営には手間と時間を要しますが、長期的に同じ場所で暮らすことを前提とすれば、そこまで問題にはなりにくい側面もあります。
リフォーム・リノベーションの自由度の比較
マイホームであれば、自分の判断で内装や設備を変更できる点で自由度が高いといえます。
老後の生活に合わせたバリアフリー化や設備更新など、自宅を最適な環境に整えることが可能です。賃貸物件では基本的に改修の自由は限られ、原状回復が求められるケースも多いので、生活スタイルの変化に十分に対応できないことがあります。
暮らしやすさ・安心感の比較
マイホームを所有していると、住まいに対する心理的な安心感や自立意識が高まりやすいといえます。
慣れ親しんだ地域や近隣住民との関係も維持しやすく、老後の安定した暮らしに貢献します。一方、賃貸は住み替えの柔軟性がある反面、更新や退去のおそれがつきまといます。
比較でわかった!老後に持ち家で暮らすメリット・デメリット
ここでは、老後に持ち家で暮らすメリット・デメリットについて解説します。以下に、老後に持ち家で暮らすメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
| メリット | デメリット |
| ローン完済後は住居費が大幅に軽減される | 管理や手続きは自己責任で対応が必要 |
| 売却やリバースモーゲージなど、資産として活用可能 | 築年数に応じた修繕費や更新費用が定期的に発生 |
| 所有している安心感があり、転居リスクが少ない | 医療・買い物施設への距離などにばらつきがある |
| リフォームや設備更新を自由に行える | 地域や築年数により、思い通りに売却できないおそれがある |
ここからは、持ち家のメリット・デメリットをさらに詳しく解説します。
持ち家のメリット
持ち家を所有している最大の利点は、老後における住居費の安定性と軽減です。
一般的に、住宅ローンを定年前に完済していれば、老後は家賃支出が発生しないため、住居費が大きく抑えられます。
賃貸住宅のように月々の家賃を支払い続ける必要がないことは、年金収入に頼る老後の家計にとって非常に大きな安心材料となります。
また、毎月必要となる費用も限定的であり、主に固定資産税、火災保険、必要に応じた修繕費にとどまります。住宅ローンを計画的に繰り上げ返済することで、さらに将来の支出負担を軽くすることが可能です。
さらに、「住まいが自分の資産である」という事実は、精神的な安心感にもつながります。
住み慣れた地域やご近所とのつながりを大切にしながら、終の棲家として安心して住み続けられる点も大きな魅力です。
持ち家のデメリット
一方、持ち家には所有することによる責任やコスト面でのリスクも存在します。
最も大きいのは、築年数とともに発生する経年劣化や老朽化に伴う修繕・改修費用です。屋根や外壁、水回り、給湯設備などは定期的にメンテナンスが必要で、まとまった支出が発生するおそれがあります。
これらの費用は突発的で予測が難しく、老後の資金計画に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、古い住宅の場合には耐震性能や断熱性能が現代基準を満たしていないことも多く、生活の快適性や安全性に課題が残るケースもあります。
バリアフリー対応がされていない場合には、将来的に大規模な改修工事が必要になることもあり、負担は決して軽くありません。
さらに、立地によっては、医療機関や商業施設、公共交通機関へのアクセスが悪い場合もあり、年齢を重ねるにつれて生活の不便さが増すおそれもあります。
比較でわかった!老後に賃貸で暮らすメリット・デメリット
ここでは、老後に賃貸で暮らすメリット・デメリットについて解説します。以下に、老後に賃貸で暮らすメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご確認ください。
| メリット | デメリット |
| 体調やライフステージに応じて自由に住み替えできる | 年金生活でも家賃の支払いが生涯続き、負担が増すおそれがある |
| 設備修繕や建物管理は原則オーナー側の対応で負担が少ない | 改修やリフォームに制限があり、自由度が低い |
| 保証会社の利用により契約のしやすさが向上しているケースもある | 高齢者は審査や保証人の確保が難しく、入居できない物件もある |
| 資産の維持・相続手続きが不要で身軽に生活できる | 更新拒否や立ち退きのおそれがあり、長期的な安定性に欠ける |
ここからは、賃貸のメリット・デメリットをさらに詳しく解説します。
賃貸のメリット
賃貸住宅の最大の魅力は、ライフスタイルや健康状態の変化に柔軟に対応できる住み替えのしやすさにあります。
階段の上り下りが困難になるなどの新たなニーズが出てくるなかで、住環境をスムーズに見直せるのは賃貸ならではの大きな強みです。
65歳以降にバリアフリー設計の物件やサービス付き高齢者向け住宅へ移る、子育て世帯の近くに住み替えるなど、ライフステージに応じて柔軟な住まい選択が可能です。
こうした自由な選択肢が、生活の質を高めるうえで大きな役割を果たします。
また、物件のメンテナンスや修繕対応は基本的に大家や管理会社の責任となるため、自分で対応する負担が少なく済むでしょう。
賃貸のデメリット
一方、賃貸住宅には年齢を重ねるほど契約条件が厳しくなるといった現実的なデメリットがあります。
高齢者になると、貸主側のリスク懸念から入居審査に通りにくくなるケースが多く、特に単身世帯の場合はその傾向が顕著です。
さらに、賃貸では家賃を一生支払い続ける必要があるという点も大きな負担となるでしょう。
退職後の年金収入のみで生活する中、毎月の家賃が5〜10万円といった水準で継続して発生するのは、生活資金全体にとって大きな圧力となります。
室内の改修やリフォームに制限があるため、介護が必要になった際の住環境の整備が思うように進まないこともあります。
老後の持ち家で後悔しないためのポイント
ここからは、老後の持ち家で後悔しないためのポイントについて解説します。
- 定年を見据えて余裕のある資金計画を立てておく
- 老後に暮らしやすい住宅や環境を選ぶ
- 繰り上げ返済も視野に入れる
定年を見据えて余裕のある資金計画を立てておく
住宅を持ち続けるには、固定資産税・修繕費・保険料など、定期的な支出が生涯にわたり発生します。
そのため、現役時代から退職後の収支バランスを想定し、無理のない返済と生活維持ができるように、長期的な資金計画を構築しておくことが不可欠です。
年金収入だけでは賄いきれない費用も想定されるため、生活予備資金や修繕積立の準備があるかどうかが、安心して住み続ける鍵となります。
老後に暮らしやすい住宅や環境を選ぶ
定年後の暮らしを見据え、住まいの機能性だけでなく、周辺環境の利便性や将来の生活動線にも配慮が必要です。
バリアフリー設計、階段の少なさ、病院や商業施設へのアクセスの良さなど、年齢を重ねた際に不便を感じにくい物件を選ぶことがポイントです。
また、近隣との関係性や自治体のサポート体制も含めた“地域環境の質”にも目を向けることで、老後の生活における安心感が格段に高まります。
繰り上げ返済も視野に入れる
住宅ローンの返済を定年後に持ち越さないことは、老後の家計を安定させるうえで非常に効果的です。
余裕資金があるうちに繰り上げ返済を検討し、ローン完済の時期を前倒しすることで、毎月の支出負担を軽減できます。
金利の高い初期段階での返済は、利息負担の削減に直結します。
ただし、無理な一括返済は資金ショートのリスクにもつながるため、教育費や老後資金とのバランスを見ながら、計画的に実施することが重要です。
老後の賃貸で後悔しないためのポイント
ここからは、老後の賃貸で後悔しないためのポイントを解説します。
- 家賃債務保証制度の利用を検討する
- なるべく家族を保証人にする
- 高齢者向けの賃貸物件を探しておく
家賃債務保証制度の利用を検討する
高齢になると、賃貸契約において「支払い能力」や「保証人の確保」が課題になることが増えてきます。そうした背景から注目されているのが、家賃債務保証制度の活用です。
これは、民間の保証会社が家賃の滞納時に支払いを肩代わりする仕組みで、保証人を用意できない高齢者にとって心強い選択肢となります。
また、自治体や社会福祉法人が運営する制度もあり、条件に合えば利用可能です。
なるべく家族を保証人にする
高齢者が新たに賃貸契約を結ぶ際、依然として連帯保証人を求められるケースが多くあります。
その際、最も信頼性が高いのは家族を保証人とする方法です。親族であれば、貸主からの信用を得やすく、契約もスムーズに進みます。
ただし、保証人には継続的な責任が発生するため、家族との事前の合意や理解が欠かせません。また、保証人となる家族の経済状況や健康状態にも注意が必要です。
万が一に備え、家族と早い段階で話し合いをしておくことが、賃貸継続の安定性を高めるカギとなります。
高齢者向けの賃貸物件を探しておく
将来的な住まいの確保に備え、あらかじめ高齢者歓迎の賃貸物件や、高齢者専用の住宅情報を調べておくことが重要です。
一般的な物件に比べて、バリアフリー設計や緊急通報システムの整備がされている場合も多く、身体的な変化に対応した住環境を得られます。
また、オーナー側も高齢者の入居に理解があるケースが多いため、入居審査に通りやすい点も利点です。年齢が上がるにつれて物件選択の幅は狭くなるため、早期の情報収集と住み替え準備が、賃貸生活における「後悔」を減らす大きな一歩となります。
疑問があればぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
老後は持ち家と賃貸どちらがお得か実際にシミュレーション
ここからは、老後に持ち家と賃貸どちらがお得かを実際にシミュレーションします。それぞれに対して条件を設定しながら解説します。
- 持ち家のシミュレーション
- 賃貸のシミュレーション
- 持ち家と賃貸のシミュレーション結果
持ち家のシミュレーション
持ち家のシミュレーションを行うにあたり、以下の条件を設定します。
| ● 35歳で新築一戸建て(郊外・3LDK・土地付き)を購入
● 購入価格:4,500万円(土地1,500万円+建物3,000万円) ● 頭金:500万円、借入額:4,000万円 ● 住宅ローン:固定金利1.6%、35年返済 ● 固定資産税:年間12万円(建物+土地) ● 修繕費:築後10年以降、10年ごとにまとまった修繕を実施(1回あたり150万円) ● 外構・屋根・給湯器など経年メンテナンス費も考慮 |
この条件の場合、シミュレーションの結果は以下のようになります。
| 料金の種類 | 相場 |
| ローン返済総額 | 約5,230万円 |
| 固定資産税 | 50年間で約600万円 |
| 修繕費(10年×4回) | 約600万円 |
| 初期費用(頭金・登記・諸経費含む) | 約700万円 |
| 総住居費用 | 約7,130万円 |
※あくまで概算であり、地域や物件条件などによって異なる
総費用は約7,130万円という結果になりました。
賃貸のシミュレーション
賃貸のシミュレーションを行うにあたり、以下の条件を設定します。
| ● 35歳から85歳まで賃貸住宅に居住
● 35〜60歳:3LDK、家賃14万円、共益費2万円 ● 61〜85歳:2LDK、家賃11万円、共益費1万円 ● 契約更新:2年ごと、更新料は家賃1ヶ月分 ● 初期費用:家賃の6ヶ月分(敷金・礼金・仲介手数料など) |
結果は以下のようになります。
| 料金の種類 | 相場 |
| 35〜60歳の住居費用 | 約4,800万円 |
| 61〜85歳の住居費用 | 約3,600万円 |
| 更新料 | 50年間で約300万円 |
| 初期費用 | 約156万円 |
| 総住居費用 | 約8,856万円 |
※あくまで概算であり、地域や物件条件などによって異なる
総費用は約8,856万円という結果になりました。
持ち家と賃貸のシミュレーション結果
持ち家と賃貸の総費用をシミュレーションで比較すると、以下のようになりました。
| 種類 | 総費用 |
| 持ち家 | 約7,130万円 |
| 賃貸 | 約8,856万円 |
戸建ての購入・維持費用の合計は約7,130万円、賃貸を選んだ場合の50年間の住居費用は約8,856万円となりました。
持ち家(戸建て)の方が約1,726万円、生涯の住居費を抑えられる結果です。
ただし、戸建ては老後の修繕コストや周辺環境による生活のしやすさに左右されるため、購入時の立地選定が非常に重要です。
一方、賃貸は柔軟性に優れていますが、高齢期の入居難易度や家賃負担の継続が課題となります。
老後の持ち家・賃貸に関するよくある質問
最後に、老後の持ち家・賃貸に関するよくある質問を紹介します。
- 賃貸と持ち家で1,300万円の差って本当?
- 老後に家賃が払えないと感じたらどうする?
- 40歳で家を買うか賃貸か迷ったらどうすればいい?
- 老後一人暮らしの生活費は平均いくら?
賃貸と持ち家で1,300万円の差って本当?
条件によっては生涯の住居コストに1,300万円以上の差が出るケースは十分にあり得ます。
たとえば、持ち家を35歳で購入し、定年までにローンを完済した場合、以降は固定資産税や修繕費のみで済みます。
一方、賃貸の場合は高齢期も家賃支払いが継続し、家賃の累積額が大きくなります。特に都市部で家賃が高額なエリアに住み続けると、50年で約9,000万円近くかかることもあるでしょう。
具体的なシミュレーションに基づく比較とその背景については、以下の記事でも詳しく解説されています。ぜひご参照ください。
| 【あわせて読みたい】 |
老後に家賃が払えないと感じたらどうする?
老後に家賃が払えないと感じたら、「公的支援制度」の活用を検討するのが手段の1つです。
たとえば、生活保護制度や住宅確保給付金、高齢者向けの家賃補助制度などが自治体によって提供されていることがあります。
また、収入や支出を見直し、家賃の安い物件への住み替えも選択肢です。さらに、高齢者でも入居しやすい「高齢者向け賃貸住宅」も検討する価値があります。
早めの情報収集と相談が鍵となります。
40歳で家を買うか賃貸か迷ったらどうすればいい?
40歳は、住宅取得を検討する上で重要なタイミングです。
住宅ローンを利用する場合、返済期間や老後の生活費への影響を踏まえた慎重な判断が求められます。定年退職までに完済できる返済計画を立てられるかが1つの判断基準です。
安定した収入があり、長期的に同じエリアに住む予定がある場合は、購入も現実的な選択肢となるでしょう。
一方で、転勤の可能性が高い・柔軟性を重視したいという方は賃貸の方が適している場合もあります。家族構成や今後のライフプランをもとに、総合的に判断することが重要です。
老後一人暮らしの生活費は平均いくら?
総務省の家計調査(単身高齢者世帯)によると、老後一人暮らしの平均的な生活費は月約14〜16万円程度とされています。
この中には、食費・光熱費・保険・医療・趣味・交際費などが含まれており、住居費は別枠で考える必要があります。
持ち家でローンを完済している場合は住居費を月数千円に抑えられることもありますが、賃貸であれば家賃が大きな負担になるでしょう。
賃貸で月6〜8万円の物件に住む場合、全体の生活費は20万円近くに達する場合もあるため、住居費の比重が生活設計に大きく影響します。
老後の住まい選びは慎重に検討しよう
この記事では、老後の住まいは持ち家と賃貸どちらがお得かについて解説しました。
持ち家と賃貸について、シミュレーションやメリット・デメリットの比較などを通じて検証した結果、総住居費の観点では持ち家の方がコストを抑えやすいことがわかりました。
一方、持ち家には修繕費・固定資産税といった維持コスト、立地選定や老朽化リスクへの対策も必要です。
賃貸には、柔軟な住み替えや管理の手間が少ないといった利点があるものの、高齢期の入居ハードルや家賃支払いの継続が大きな課題となります。
最終的に、老後の住まいを決めるのは自分自身です。それぞれのメリット・デメリットや実際の居住費用を踏まえて、慎重に判断しましょう。
住宅ファクトリーでは、住宅ローン審査の通過実績が多数あります。複数のお借入がある場合でも1本化できる「おまとめローン」を強みとしてご提案しております。
老後に備えた家づくりも、お客様に寄り添いながら最適なアドバイスをいたします。将来を見据えた家づくりをご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!