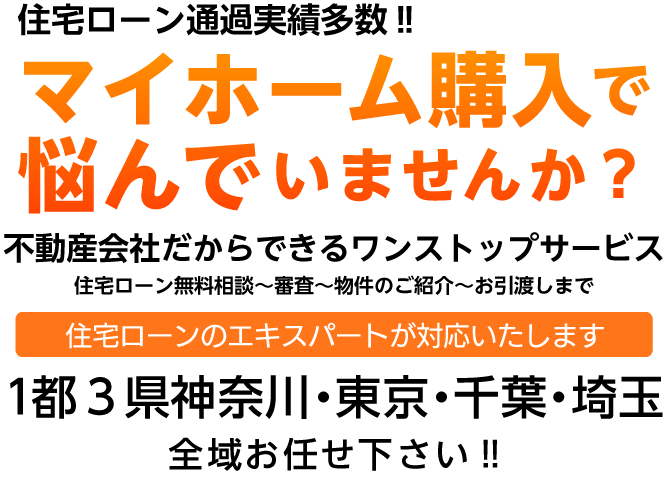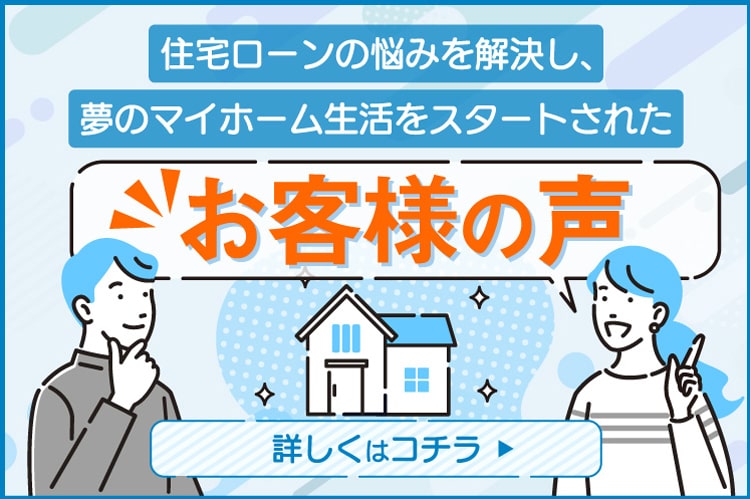マイホームを購入すると、毎年かかるランニングコストの1つに「固定資産税」があります。
税額は、建物の大きさや面積、立地などによって異なりますが、意外に高く感じている人も少なくありません。これから家を取得する人のなかにも、固定資産税がいくらになるのか気になっている人もいるでしょう。
ここでは、税額の相場や計算方法、節税につながる軽減措置など、固定資産税の基本的な情報をまとめてお伝えします。固定資産税額のシミュレーションも解説するので、これからマイホームの購入を検討されている人は、ぜひ参考にしてください。
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
一戸建ての固定資産税とは?
固定資産税とは、建物や土地といった不動産などの固定資産に課せられる地方税です。
税額は、その資産の評価額に応じて決まり、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に対し、市町村(東京都23区内では都)が課税します。固定資産税の税率は原則1.4%ですが、市町村によっては税率が異なることもあります。
一戸建ての場合は、建物と土地の固定資産税がそれぞれ計算され、その合計金額を納めます。
建物と土地をわけるのは、それぞれの評価額が年によって異なるためです。たとえば、建物の場合、経年劣化により築年数の古い家ほど資産価値は下がります。そのため、建物の固定資産税も古い建物ほど安くなる傾向にあります。
一方、土地は古くなっても価値は変わりません。むしろ、周辺環境の変化で人気が高まると価値が上がり、固定資産税が増える可能性もあります。
不動産会社から物件を購入する際には、固定資産税を売主と買主で日割清算するケースが多く見られます。
たとえば、7月1日に物件を購入した場合、1月1日〜6月30日までは売主が、7月1日〜12月31日までは買主が負担するといった契約が通例です。
※参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|不動産と税金|東京都主税局
一戸建ての固定資産税は平均いくら?
一般論として、一戸建ての固定資産税はおおよそ10〜15万円といわれます。
ただし、固定資産税は建物の大きさや立地など、さまざまな要件によって異なりますので、一概にはいえません。
特に、注文住宅は建材や設備が一軒一軒異なるので、実際に建ててからでなければわからないのが実情です。
目安として、総務省が実施した「地方税に関する参考計数資料(令和7年度)」のデータを参考に税額を見ていきましょう。東京都・神奈川県における1人当たりの固定資産税・都市計画税の合計額は以下のとおりです。
| 東京都(円) | 神奈川県(円) | |
| 土地:固定資産税(人口1人当たり) | 6万5,526 | 3万1,503 |
| 家屋:固定資産税(人口1人当たり) | 4万5,112 | 3万3,760 |
| 都市計画税(人口1人当たり) | 2万4,207 | 1万4,876 |
| 合計 | 13万4,845 | 8万139 |
※参考:令和7年度 地方税に関する参考計数資料(P185〜186,P191)|総務省
参照すると、税収を人口で割った1人あたりの税収が全国で最も高いのは東京都で、神奈川県も全国的に高いほうです。
なお、東京・神奈川ともにエリアにより地価が異なるため、都市部にある地域はさらに固定資産税・都市計画税の負担金額が多くなります。
一戸建ての固定資産税の計算方法
固定資産税額は、課税標準額をもとに計算します。
各市町村(東京都23区内では東京都)が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、土地と家屋の価値を評価した「固定資産評価額」が算出されます。
固定資産評価額は3年に一度評価替えが行われ、直近は令和6年度、次回は令和9年度に実施される予定です。ここでは、一戸建ての固定資産税の計算方法について解説します。
※参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|不動産と税金|東京都主税局
土地の固定資産税を計算
土地の固定資産税の計算式は、以下のとおりです。
| 土地の固定資産税額 = 土地の課税標準額 × 標準税率(1.4%) |
たとえば、土地の課税標準額が500万円の例で計算してみましょう。
| 土地の固定資産税額 = 500万円×1.4%=7万円 |
上記のとおり、土地の固定資産税額は7万になります。
建物の固定資産税を計算
次に、建物の固定資産税を試算してみましょう。なお、税率は土地と同じ1.4%です。
| 建物の固定資産税額 = 建物の課税標準額 × 標準税率(1.4%) |
たとえば、建物の課税標準額が1,000万円の場合、固定資産税は以下のとおりです。
| の固定資産税額 = 1.000万円×1.4%=14万円 |
建物の固定資産税額は14万になります。建物は年々老朽化していくため、評価替えごとに税額が安くなるのが一般的です。
土地・建物の固定資産税を合算
一戸建ての固定資産税額は、土地と建物の分を合算することになります。
計算方法は、以下のとおりです。
| 固定資産税額 = 課税標準額(土地+家屋) × 標準税率 (1.4%) |
たとえば、課税標準額が土地は500万円、家屋が1,000万円である一戸建ての場合は課税標準額の合計が1,500万円で、以下のように計算します。
| 固定資産税額 = 1,500万円× 1.4%=21万円 |
このケースの一戸建ての場合では、固定資産税が21万円となります。
一戸建ての固定資産税の支払い方法・納税時期
一戸建てなどの不動産所有者に、市区町村から毎年4月〜6月頃送られてくるのが納税通知書です。通知書には、土地と家屋それぞれの評価額や課税標準額、税額、納税時期(納期限)が記載されています。
固定資産税は基本的に年4回に分けて納付するのが一般的ですが、一括払いも可能です。
自治体により異なりますが、おおよそ以下の時期に納付します。
- 第1期: 4月下旬〜6月頃
- 第2期:7月下旬〜9月頃
- 第3期:12月頃
- 第4期:翌年2月頃
納期限を過ぎると、延滞金が発生する場合があるため、期限内に納めるようにしましょう。
支払い方法はさまざまな方法があり、主に以下のような納付方法があります。
- 現金払い(金融機関や市区町村の窓口・コンビニエンスストア)
- 口座振替(自動引き落とし)
- クレジットカード払い(すべての自治体が対応しているわけではない)
- スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Pay、楽天ペイなど)
- ペイジー
- 電子マネー
支払い方法や納税時期は、お住まいの市区町村によって異なるため、必ず送付された納税通知書を確認してください。
※参考:納税通知書の見方|秩父市
一戸建ての固定資産税に適用できる軽減措置
固定資産税の通知書には固定資産評価額や課税標準額が記載されており、税額の基となる金額は課税標準額を使用します。基本的に課税標準額と固定資産評価額は同額です。
ただし、特例措置や調整措置が適用されると、評価額よりも課税標準額のほうが低くなります。ここでは、一戸建ての固定資産税に適用できる軽減措置について見ていきましょう。
- 建物の固定資産税に適用できる軽減措置
- 土地の固定資産税に適用できる軽減措置
建物の固定資産税に適用できる軽減措置
建物の固定資産税に適用できる主な軽減措置は、主に以下の2つです。
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。減額を受けるための要件と減額内容は以下のとおりです。
| 新築住宅に係る固定資産税の減額措置 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置 | |
| 減額を受けるための要件 | ● 令和8年3月31日までに新築された住宅
● 居住用部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下 ● 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上 |
● 左記の要件に加え、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅 |
| 減額される範囲 | ● 120㎡以下の部分が2分の1 | ● 120㎡以下の部分が2分の1 |
| 減額される期間 | ● 一般の住宅は新築後3年間
● 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は新築後5年間 |
● 一般の住宅は新築後5年間
● 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は新築後7年間 |
※参考2:新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度 |横浜市
たとえば、床面積150平方メートルの一戸建ての場合は、120平方メートルまでの部分が減額対象となり、残りの30平方メートルは減額対象外です。
なお、新築住宅に係る固定資産税の減額制度を受ける際に申告する必要はありません。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置で減額を受ける場合は、申告書に認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付しましょう。
なお、自治体の窓口に申告することが必要です。
土地の固定資産税に適用できる軽減措置
土地の固定資産税に適用できる主な軽減措置は、住宅用地の特例です。
土地の評価額は住宅用地の特例による軽減措置(住宅用地の特例)を受けた場合、固定資産税が6分の1に軽減されるため、マイホームで使用する土地の固定資産税を大幅に軽減します。
住宅用地は、その面積に応じて以下2つの区分に分けられ、それぞれ異なる割合で課税標準額が減額されます。
| 区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 固定資産税の本則課税標準額 |
| 小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200m2以下の部分 | 価格×6分の1 |
| 一般住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200m2を超える部分 | 価格×3分の1 |
※参考:土地についての特例 |横浜市
たとえば、300平方メートルの住宅用地の場合は、200平方メートルが「小規模住宅用地」として1/6の減額、残りの100平方メートルが「一般住宅用地」として1/3を減額されます。
一戸建ての固定資産税がいくらかかるのか実際にシミュレーション
ここでは、一戸建ての固定資産税がいくらかかるのか実際にシミュレーションしてみましょう。所在地は横浜市とし、以下の条件でシミュレーションを行います。
| 【土地】
● 面積:120平方メートル ● 課税標準額:3,000万円 ● その他:住宅用地(小規模住宅用地200m2以下に該当) 【建物】 ● 種類:木造新築住宅 ● 築年数:新築後2年目 ● 延床面積:100平方メートル ● 課税標準額:2,000万円 |
まず、最初に土地の課税標準額を算出します。土地の面積が120平方メートルで、小規模住宅用地の特例に該当するため、課税評価額が6分の1に減額されます。
計算式は以下のとおりです。
| 土地の課税標準額 = 3,000万円 × 1/6 = 500万円 |
課税標準額500万円に対し税率1.4%をかけると、土地の固定資産税額が算出できます。
| 土地の固定資産税額=500万円 ×1.4%=7万円 |
小規模住宅用地の特例が適用されなかった場合は、土地の課税標準額3,000万円に対して1.4%がかけられ、固定資産税額は42万円になります。
小規模住宅用地の特例が適用された場合は7万円で、差額は35万円です。このように、小規模住宅用地の特例が適用されると、土地の固定資産税額が大きく減額されます。
次に、建物の固定資産税額を計算してみましょう。新築後2年目なので、新築住宅に係る固定資産税の減額制度が適用され、固定資産税が半額になります。
計算式は以下のとおりです。
| 建物の固定資産税額=2,000万円 ×1.4%× 1/2=14万円 |
この場合、建物の固定資産税額は14万円になります。減額される前と後の固定資産税の比較表は、以下のとおりです。
| 減額される前 | 減額された後 | |
| 土地の固定資産税額 | 42万円 | 7万円 |
| 建物の固定資産税額 | 28万円 | 14万円 |
| 合計税額 | 70万円 | 21万円 |
上記のように、減額措置を受けない場合と受けた場合では納める税額が大きく異なります。
一戸建ての固定資産税の平均額を把握して抑える工夫をしよう
一戸建てを所有すると毎年発生する固定資産税は、家計にとって無視できないランニングコストです。
たとえば、横浜市では住宅地の平均価格が約25.7万円/m2(令和7年地価公示)ですが、同じ市内でもエリアにより価格には差があります。自分が所有する土地の平均相場価格を知ることで毎年届く納税通知書の内容を適切に評価できるようになります。
住宅用地の特例や新築住宅の減額措置など、軽減措置の適用状況を確認しておくことも必要です。新築住宅の減額措置を受けている場合は、期間が終了する時期も把握しておきましょう。
住宅用地の特例は期限がありませんが、新築住宅の減額措置は適用期間が定められているため、終了時期を認識しておくことが重要です。
※参考:令和7年 地価公示のあらまし(横浜市分)(P1)|横浜市
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!