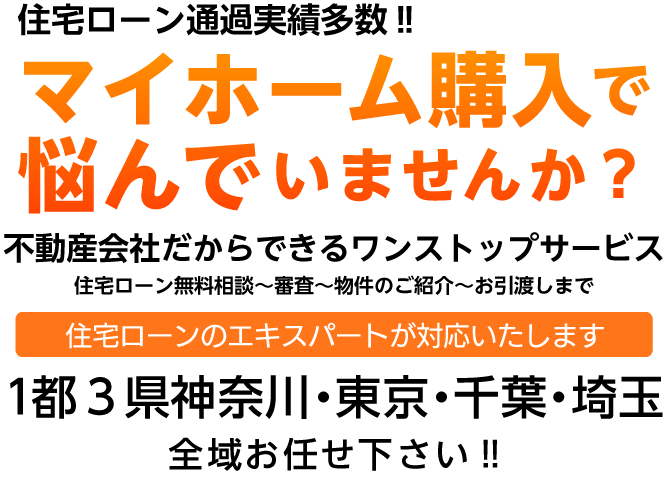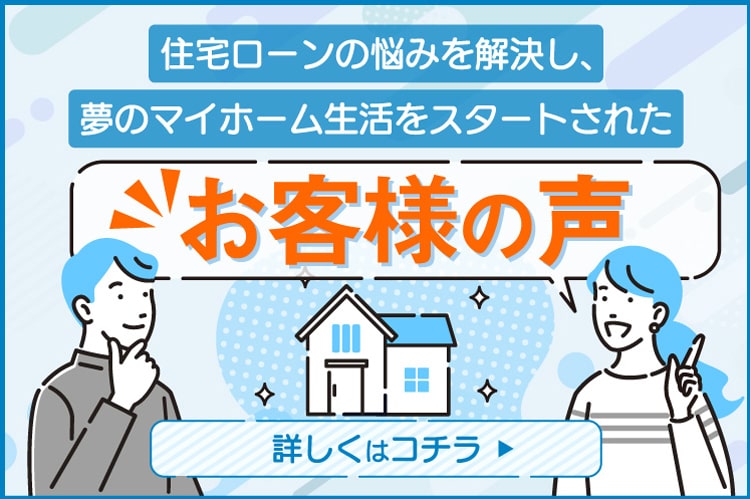この記事では、住宅ローンと車のローンの併用可否について解説します。
家づくりに伴い住宅ローンの借入れを検討している人の中には、すでに別のローンを借入れしているケースもあります。ローンの1つとして挙げられるのが車のローンです。
車のローンと同様に住宅ローンでも審査に通過する必要があるので「複数の借入れがあることで審査に通らないのではないか」と不安に感じている人は少なくありません。
この記事では、住宅ローンと車のローンの併用や、審査に通るコツについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 住宅ローンと車のローン(マイカーローン)の併用はできるのか
- 住宅ローンと車のローン併用による審査の影響
- 住宅ローンと車のローン併用の審査に落ちる原因
- 車のローンと住宅ローン併用の審査に通るコツ
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
住宅ローンと車のローン(マイカーローン)の併用はできるのか
住宅ローンと車のローンの併用は可能です。住宅と車のローンは、それぞれ用途が異なるため、同時に借入れできます。
住宅ローンは高額で長期間の借入れとなるため、返済比率や信用情報が厳しく審査されます。
一方、車のローンは比較的短期間の借り入れですが、他のローンとの併用で返済能力が問われる場合があります。併用する際は、総返済額や家計の負担を事前に試算し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
住宅ローンと車のローン併用で重要となるのは返済負担率
住宅ローンと車のローンを同時に利用する際に重要となるのが、返済負担率です。
返済負担率とは、年収に対するローンの年間返済額の割合を示す指標で、金融機関の審査においても非常に重要な要素となります。
住宅ローンは、一般的に長期間にわたり大きな金額を借入れするので、返済負担率が高くなると車のローンの審査にも影響を及ぼすことがあるでしょう。
ここからは、返済負担率について以下2点を解説します。
- 返済負担率の計算方法
- 併用する場合の理想的な返済負担率の目安
順番に見ていきましょう。
返済負担率の計算方法
返済負担率は、以下の計算式で求められます。
| 返済負担率 = 年間のローン返済額 ÷ 年収 × 100(%) |
これは、ローンの返済額が収入に対してどの程度の割合を占めるのかを示す重要な指標であり、金融機関の審査基準の1つです。返済負担率が高すぎると、家計の圧迫につながるだけでなく、審査で不利になる場合があります。
たとえば、年収500万円の人が住宅ローンで年間100万円を返済している場合、返済負担率は「100万円 ÷ 500万円 × 100 = 20%」となります。車のローンの年間返済額として50万円が加わる場合、返済負担率は「150万円 ÷ 500万円 × 100 = 30%」です。
ローンを申し込む際は、現在の収入と返済額を正確に計算し、返済負担率が適正範囲内に収まるように調整することが重要です。
併用する場合の理想的な返済負担率の目安
住宅ローンと車のローンを併用する際、理想的な返済負担率は年収の25%以下が望ましいとされています。
併用する場合、車のローンを含めると当然ながら返済負担率が上昇し、家計の負担が増加する場合があるでしょう。そのため、将来的に金利が上昇した場合や収入が減少した場合に、返済負担率が高すぎると家計が圧迫され、生活に影響を及ぼします。
たとえば、年収600万円の人が住宅ローンで年間150万円を返済している場合、返済負担率は「150万円 ÷ 600万円 × 100 = 25%」となります。仮に、車のローンの年間返済額50万円が加わると200万円になり、返済負担率は「200万円 ÷ 600万円 × 100 = 33.3%」です。
この場合、金融機関によっては「返済負担率が高すぎる」と判断されるおそれがあり、審査が通りにくくなることがあります。
住宅ローンと車のローン併用による審査の影響
住宅ローンと車のローンを併用すると、金融機関の審査に影響を及ぼすおそれがあります。審査時に重視される返済負担率が高くなるため、慎重な資金計画が必要です。
一般的に、金融機関は返済負担率を基準の1つとして借入可能額を判断します。他にも、申込者の収入や職業、信用情報なども細かくチェックされるでしょう。
住宅ローンと車のローンを併用する際は、事前に現在の返済負担率を計算し、無理のない範囲で借入額を調整することが重要です。
また、住宅ローンの審査を優先し、車のローンを後回しにすることで、審査に通る可能性を高められます。無理のない返済計画を立て、審査に備えることが重要です。
住宅ローンと車のローン併用の審査に落ちる原因
ここからは、住宅ローンと車のローン併用の審査に落ちる原因について解説します。
- 提出書類に誤りがある
- 過去に滞納歴がある
- 借入希望額が収入に見合っていない
- その他の審査基準を満たしていない
上記4点について、それぞれ見ていきましょう。
提出書類に誤りがある
住宅ローンや車のローンを申し込む際には、収入証明書や本人確認書類、税金の納付証明書など、さまざまな書類を提出することが必要です。
書類に不備や誤りがあると、金融機関は正確な審査を行えず、結果として審査に落ちるおそれがあります。
年収を証明する源泉徴収票や、確定申告書の記載が実際の収入と異なる場合、勤務先の在籍確認が取れない場合などに審査が進まないことがあるでしょう。
過去に滞納歴がある
住宅ローンや車のローンの審査では、信用情報が大きく影響します。金融機関は信用情報機関のデータを参照し、申込者の過去の借入れ履歴や返済状況を確認します。
もし、過去にクレジットカードや携帯料金、他のローンの支払で滞納した履歴がある場合、審査に落ちるおそれがあるでしょう。
3ヶ月以上の長期滞納があった場合や債務整理をした履歴がある場合は、金融機関の審査基準に抵触し、借入れが難しくなる傾向にあります。
なお、信用情報は個人信用情報機関で開示請求を行うことで確認できます。
審査に申し込む前に自身の信用情報をチェックし、万が一問題がある場合はローン申込みの前に信用を回復するための対策を講じることが重要です。
借入希望額が収入に見合っていない
住宅ローンと車のローンを併用する際、借入希望額が収入に対して過剰であると、審査に落ちるおそれがあります。
金融機関は申込者の年収を基に「返済負担率」を計算し、割合が適正であるかを判断します。
一般的に、住宅ローンの返済負担率は25%以下が望ましいとされ、車のローンを加えるとさらに負担が増すでしょう。その場合、金融機関の審査基準を超えてしまうことがあります。
たとえば、年収500万円の人が住宅ローンの年間返済額として150万円、車のローンで50万円を希望すると、返済負担率は40%に達し、審査が厳しくなるおそれがあります。
無理のない範囲で借入れを設定し、審査基準をクリアできるよう調整することが重要です。
その他の審査基準を満たしていない
住宅ローンと車のローンの審査では、収入や信用情報以外にも、さまざまな基準が考慮されます。たとえば、「勤続年数」や「雇用形態」は審査に大きく影響する要素です。
一般的に、正社員での勤務が長いほど審査に有利に働きますが、転職直後や契約社員・派遣社員の場合は、収入の安定性が懸念されるため、審査が厳しくなることがあります。
また、既存の借入れ状況も審査基準の1つです。特に、クレジットカードのキャッシング枠を利用している場合や消費者金融の借入れがある場合は、審査に影響を与えるおそれがあります。
すでに多くの借入れがある場合、金融機関は「返済能力が低い」と判断することがあるため、審査に申し込む前に不要な借入れを整理し、可能な限り完済しておくことが重要です。
※参考:令和4年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書|国土交通省
車のローンと住宅ローン併用の審査に通るコツ
ここからは、車のローンと住宅ローン併用の審査に通るコツについて解説します。
- 無理のない返済計画を立てる
- なるべく頭金を多めに用意する
- 他のローンや借金を増やしすぎない
- 使用していないクレジットカードやローンを整理しておく
- マイホームを検討するなら住宅ローンを優先する
- 勤続年数を長くして安定した収入を証明する
- 配偶者の収入を合算する
上記について、それぞれ見ていきましょう。
無理のない返済計画を立てる
住宅ローンと車のローンを併用する際は、毎月の返済額が家計に与える影響をしっかりシミュレーションすることが重要です。
返済負担率が高くなると審査に通りにくくなるだけでなく、将来的に家計を圧迫するリスクが高まるでしょう。金融機関の審査では、一般的に返済負担率が25%以下であることが望ましいとされています。
車のローンを追加すると負担が増し、審査が厳しくなるおそれがあります。そのため、借入れ前に詳細な返済計画を立て、無理のない範囲でローンを組むことが重要です。
なるべく頭金を多めに用意する
住宅ローンや車のローンを申し込む際、借入額をできるだけ抑えるために、頭金を多めに用意することが重要です。
住宅ローンでは頭金の割合が高いほど借入額が減少し、返済負担率を抑えられるため、審査通過の可能性が高まります。
たとえば、3,000万円の住宅を購入する際に頭金を500万円用意すれば、借入額は2,500万円となり、月々の返済額を軽減可能です。
車のローンについても、頭金を入れることで借入額を減らし、金融機関の審査基準をクリアしやすくなります。無理のない範囲で頭金を準備し、ローンの負担を軽減することが重要です。
他のローンや借金を増やしすぎない
住宅ローンと車のローンを併用する際、クレジットカードのリボ払いやキャッシング、教育ローンなど、他の借入れが多いと審査に悪影響を与えるおそれがあります。
金融機関は申込者の信用情報をチェックし、既存の借入れが多い場合には「返済能力に問題がある」と判断することがあります。
そのため、住宅ローンや車のローンを申し込む前に、不要な借入れを整理し、可能な範囲で完済しておくことがおすすめです。
また、新規のローン契約は審査に影響を与えるため、住宅ローンや車のローンを申し込む前後の時期に、新たなローンを組むのは避けたほうが賢明といえます。
使用していないクレジットカードやローンを整理しておく
金融機関の審査では、実際に使用していないクレジットカードや未使用のローン枠も、借入れ可能額として判断されることがあります。
たとえば、クレジットカードに高額な利用限度額が設定されている場合、たとえ使用頻度が低くても「将来的に借入れリスクがある」とみなされることがあります。
そのため、長期間使用していないクレジットカードや不要なローン契約は、事前に解約しておくことが望ましいといえるでしょう。
また、キャッシング枠を設定している場合も審査に影響を与えるおそれがあるため、不要であれば解約することを推奨します。
マイホームを検討するなら住宅ローンを優先する
住宅ローンと車のローンを併用する場合、審査に通りやすくするためには先に住宅ローンを組んだ後に車のローンを申し込むのがおすすめです。
なぜなら、住宅ローンは高額な借入れであり、審査の際に他の借入れが少ないほうが好条件でローンを組める可能性が高いからです。
逆に、先に車のローンを組んでしまうと、住宅ローン審査時にすでに借入れがあると判断され、希望額の借入れが難しくなることがあります。
そのため、マイホーム購入を検討している場合は、まず住宅ローンを優先し、無理のない範囲で返済計画を立てた上で、車のローンを申し込むのがおすすめです。
勤続年数を長くして安定した収入を証明する
住宅ローンと車のローンの併用を検討する場合、なるべく勤続年数が長い状態で申し込むことを推奨します。
勤続年数が短い場合、返済能力が不安定と判断されるため、審査に落ちるリスクが高まるでしょう。最低でも1年以上、できれば3年以上の勤務実績があると審査で有利になります。
また、転職直後だと収入の維持を証明しづらいと判断される場合があるので、できるだけ同じ会社で勤続年数が長い状態を維持することが望ましいといえます。
また、フリーランスや個人事業主の場合、直近3年分の確定申告書や納税証明書を提出し、安定した収益があることを金融機関に示すことが求められます。 給与明細や源泉徴収票を準備し、定期的な収入があることを証明できると、ローン審査の通過率が高まるでしょう。
配偶者の収入を合算する
住宅ローンと車のローンを併用する際、単独での借入が難しい場合は配偶者の収入を合算することで審査に通りやすくなります。 これは「収入合算」や「ペアローン」と呼ばれる方法で、借入可能額を増やせる点がメリットです。
収入合算では夫婦の収入を合算し、世帯年収として審査されるため、返済比率を下げる効果もあります。 単独で年収400万円の場合と、配偶者と合わせて600万円の場合では、後者の方がローンの借入枠が広がり、審査に通る可能性が高くなります。
ただし、ペアローンの場合は双方がローン契約者となり、どちらかが返済不能になると影響が出る点に注意が必要です。
収入合算の条件や審査基準は金融機関によって異なるため、事前に相談することが重要です。
住宅ローンと車のローンを1つにまとめることはできるのか
住宅ローンと車のローンを1つにまとめることは可能ですが、方法や条件によっては制約があるため、慎重な判断が必要です。
金融機関によってはおまとめローンや借り換えローンを利用することで、住宅ローンと車のローンを1本化できる場合があります。
以下では、おまとめローンと借り換えローンの特徴を表にまとめました。
| 項目 | おまとめローン | 借り換えローン |
| 目的 | 複数のローンを一本化し、返済負担を軽減する | 既存のローンをより低金利のものに切り替える |
| 適応対象 | クレジットカードローン、消費者金融ローン、自動車ローンなど | 住宅ローンや自動車ローンなど |
| 金利 | 比較的高め(3%~10%程度) | 低金利(1%~5%程度) |
| 返済期間 | 最長10年程度(金融機関による) | 住宅ローンの場合は最長35年、自動車ローンは最長10年程度 |
| メリット | 月々の返済額を抑え、管理しやすくなる | 金利を下げることで総返済額を減らせる |
| デメリット | 総返済額が増えるおそれがある | 手数料や諸費用がかかる場合がある |
おまとめローンを利用すると、返済の管理がしやすくなる点がメリットです。
複数のローンをそれぞれ別々に返済する場合、支払日が異なり、管理が煩雑になることがあります。1本化することで返済日を統一できるので、支払忘れのリスクを減らせるでしょう。
ここからは、おまとめローンのメリット・デメリットを中心に詳しく解説します。
おまとめローンのメリット
おまとめローンのメリットは、主に以下のとおりです。
- 返済管理がしやすくなる
- 金利負担が減る可能性がある
- 毎月の返済額を抑えられる
複数の金融機関から借入があると、それぞれの支払い日や金額を管理するのが大変になります。
しかし、おまとめローンを活用すると毎月の返済が一つにまとまり、管理が簡単になるため、支払いの遅延や延滞のリスクを軽減できます。
通常、カードローンやキャッシングの金利は10%〜18%と高めですが、おまとめローンは銀行系の商品なら5%〜15%程度の金利で借りられる場合があります。
おまとめローンを利用すると、返済期間を長く設定できるため、毎月の返済額を減らし、生活に余裕を持たせることが可能です。
おまとめローンのデメリット
おまとめローンを利用するデメリットは、主に以下のとおりです。
- 返済期間が長くなり総支払額が増える場合がある
- 金利が必ずしも下がるとは限らない
- 手数料や保証料が発生することがある
おまとめローンは、毎月の返済額を減らせる一方、返済期間が延びることで総支払額が増えてしまうリスクがあります。
たとえば、100万円を3年で完済する場合と10年で返済する場合では、後者の利息が多くなり、結果的に支払う金額が増えることになります。
金融機関によっては、おまとめローンを契約する際に保証料や事務手数料が発生する場合があります。想定よりもコストがかかり、借り換えのメリットが薄れるおそれもあるでしょう。
住宅ローンと車のローンを1本化するなら住宅ファクトリー
住宅ローンと車のローンを1本化したい方は、住宅ファクトリー提携金融機関のおまとめローンをご利用ください。住宅ファクトリーでは、複数のローンを1つにまとめることで返済負担の軽減を実現できるプランを提供しています。
また、住宅ファクトリーでは住宅ローンに関する豊富な実績があり、お客様からの好評の声も多数いただいております。
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!
車のローンと住宅ローンの併用に関するよくある質問
ここでは、車のローンと住宅ローンの併用に関するよくある質問について解説します。
- 住宅ローンと車のローンの返済がきついときはどうすればいい?
- 住宅ローンと車のローンはどっちを先に組むのがいい?
- 住宅ローンがすでにあると車のローンは組めない?
疑問の解消にお役立てください。
住宅ローンと車のローンの返済がきついときはどうすればいい?
住宅ローンと車のローンの返済がきついときは以下の方法がおすすめです。
- ローンの借り換えを検討する
- 繰り上げ返済を活用する
- 金融機関に返済条件の相談をする
住宅ローン金利が高い場合は、より低金利の商品に借り換えることで月々の返済額を抑えられる可能性があります。車のローンも同様に借り換えをすることで、金利の引き下げが期待できるでしょう。
一時的に収入が増えた場合、車のローンの一部を繰り上げ返済することで、毎月の返済額を減らすことが可能です。
返済が難しい場合、一時的に返済期間の延長や、返済方法の見直しができるかどうかを金融機関に相談するのも有効な手段です。
住宅ローンと車のローンはどっちを先に組むのがいい?
一般的には、住宅ローンを先に組むのがおすすめです。住宅ローンは長期間の返済を伴う高額な借入れで、審査では「他の借入れの有無」が重要な要素となります。
そのため、先に車のローンを組んでしまうと、住宅ローンの審査時に「すでに借入れがある」と判断され、借入可能額が減少するおそれがあります。
一方、住宅ローンを先に組んでから車のローンを申し込む場合、住宅ローン審査時に影響を与えずに済むため、希望額の借入れがしやすくなるでしょう。
返済比率を理解して審査に通る準備をしよう
この記事では、住宅ローンと車のローンの併用は可能なのかについて解説しました。住宅ローンと車のローンはそれぞれ用途が異なるため、同時に借入れ可能です。
ただし、同時に借り入れることで返済負担率が高くなる場合があります。事前に計算を行い、無理のない範囲でローンを組むことが重要です。
住宅ローンと車のローンを1つにまとめる際は、住宅ファクトリーのおまとめローンをご検討ください。お客様に寄り添いながら、最適なプランをご提案します。
諦める前にぜひご相談ください!
住宅ローンのプロが対応いたします!